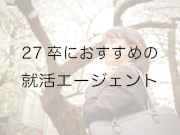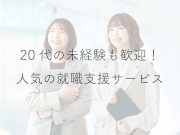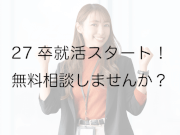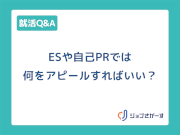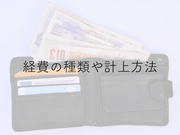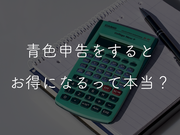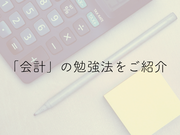Top > ライフ > 投資/株式/FX/仮想通貨
決算とは?決済との違いや、発表時期・スケジュールも解説

特に決算に関心がなくても、「決算発表」、「決算大セール」など、インターネットやテレビ、チラシなどで目にしたことがある人もいるでしょう。
ただ、「決算」という言葉自体は聞いたことがあっても、実際の意味が分からない人もいると思います。
本記事では、決算を行う意味、決済との違いや発表時期、決算の一般的なスケジュールについて見てみましょう。
決算発表が遅れるとどんな影響が出るかも解説しております。参考にしてください。
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】決算とは?決済との違いや、発表時期・スケジュールも解説
1.1年分の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書(財務諸表)を作成する
決算ってよく聞くけど一体なに?

はじめに決算の概要を紹介します。
決算の目的について述べていますので、参考にしてみてください。
1年間の業績をまとめたもの
1年間の財務状況や経営成績をまとめたものを指します。
年に1度 確定申告 をしなければならないので、ほとんどの企業で行なわれています。
企業によっては3カ月毎の業績をまとめた「四半期決算」。
半年間の業績をまとめた「半期決算」を行なう場所もあります。
決済と決算は似た言葉ですが、違う意味なので要注意!
決済と決算は、意味合いが全く違います。
決済は、売買取引を完了させる意味のことです。
例えば「商品を仕入れた企業へ代金を渡す」といった形です。
現金決済、クレジットカード決済も、売買を完了させるという意味が込められています。
決算は何月に設定されているケースが多いか?

決算は、企業によって行なう月が違います。
この章ではどの月の決算が多いかを紹介していきます。
一番多いのは3月
決算月の中で一番多いのは「3月」です。
理由は「日本での昔からの流れ」、「3月決算する企業が多い」というのが挙げられます。
3月末で決算年度を締めれば、4/1からは新年度になります。
この時期は入学式や入社式も多い時期なので、年度初めを4/1にというのは納得しやすいですよね。
3月以外で多いのは9月&12月
3月以外では、9月と12月に決算を迎える企業が多いです。
9月にする理由は「夏が終わる時期と決算の時期を合わせたい」、12月にする理由は「1月~12月の1年間でキリよく決算処理したい」などの思惑があるようです。
なお、3月の確定申告を避ける企業のなかには、「人事異動でゴタゴタしている」、「確定申告で混雑している時期に処理したくない」という理由が挙げられます。
決算報告をする意味とは?

この章では、決算報告をする意味を見てみましょう。
特に決算報告業務に携わる人は業務の大切さを理解することで、仕事のパフォーマンスも上がるはずです!
会社内で事業方針を決める
決算報告の内容によって、事業方針を決める意味合いがあります。
利益と費用のバランスを見て、事業の継続を決めるのです。
例えば売上額が少なくても、費用がかかっていなければ、その事業に力を入れた方が良いと判断するといった形です。
ただ、経営陣のなかには金額を提示されても納得しない人もいます。
その場合は、決算報告作成者が経営陣に分かりやすく説明する必要があります。
経営成績や財政状況を記録していることを株主へ証明する
決算報告は、株主へ経営成績や財政状況を示すという意味でも大事です。
決算報告をしない企業は、ブラックボックス化しているので株主から不審な目を持たれる場合もあります。
具体的な数字があるのとないのとでは、企業への印象も違います。
決算報告を延期すると、株価が下がる場合がある
なかには決算報告を延期する企業もありますが、上場企業がこれをすると株価の下落へつながる可能性が高いです。
なぜなら、「企業が何か悪いことを隠しているのではないか?」、「決算の数値をごまかそうとしているのではないか?」など、企業に対してマイナスイメージを持つ株主が増えるからです。
今まで決算報告をしていた企業が何の前触れもなく急に延期を発表したときは、株価も暴落しやすいでしょう。
決算報告準備はどこの部署が行うの?

この章では、決算準備を行う部署について見てみましょう。
決算報告準備を行うのは財務部がメイン
経理部が決算報告準備を行うと思っている人もいますが、実際は財務部がメインとなり準備をします。
経理 と財務は同じようで業務内容は違います。
経理部は主に事業内の取引実績を記録・処理する部署ですが、財務部は経理部が処理した取引実績を基に企業内の資産を管理する部署です(業務範囲は企業によって多少異なります)。
決算報告は企業内の財政状況や経営成績を分析して発表する場なので、財務部がメインとなり準備をします。
財務部がない場合は「経理部」が舵をとる
ただ、企業によっては財務部が存在しないケースもあります。
その場合は「経理部」がメインとなり決算報告準備を行います。
とくに、従業員数が少ない企業だと財務部を設けていないパターンも多いです。
この場合、取引実績の記録・処理、財政状況・経営成績の管理を同じ部署が行うケースも多く、業務的には大変になることがあります。
決算報告準備のスケジュール・工程とは?

この章からは、決算報告準備のスケジュール・工程について見てみましょう。
今回は、分かりやすく3つのステップに分けて紹介します。
1.1年分の損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書(財務諸表)を作成する
決算報告資料のメインとなる財務諸表を作成します。
これらの資料が、企業の財政状況・経営成績を示す金額の表になるのです。
作成する際は、日々の取引内容を示した仕訳の内容を 財務諸表 に転記して作成されます。
次からは、3つの表について見てみましょう。
損益計算書とは?
損益計算書は別名「PL」と呼ばれる表で企業の経営成績を表したものです。
分かりやすく言えば「黒字」か「赤字」か分かる表です。
「費用」、「収益」に分類される勘定科目のみを使用します。
下記にて勘定科目の一例を紹介します。
~費用の勘定科目~
- 売上原価
- 支払家賃
- 支払利息
- 減価償却費
- 修繕費
- 給料
~収益の勘定科目~
- 売上
- 固定資産売却益
- 有価証券利息
- 受取利息
貸借対照表とは?
貸借対照表は別名「BS」とも呼ばれており、財政状態を示した表です。
企業内に、どのぐらいの資産(負債)が残っているか分かります。
なお勘定科目は、「資産」、「負債」、「純資産」の3種類を使います。
下記にて勘定科目の一例を紹介します。
~資産~
- 現金
- 受取手形
- 貸付金
- 売掛金
- 有価証券
- 固定資産(土地、車両運搬具、備品、機械装置など)
~負債~
- 買掛金
- 支払手形
- 借入金
~純資産~
- 資本金
- 利益剰余金
- 資本剰余金
- 自己株式
キャッシュフロー計算書とは?
キャッシュフロー計算書は、キャッシュ(現金、普通預金、当座預金など)の流れを示した表です。
企業が黒字だったとしても、キャッシュの流れが活発ではないと倒産してしまいます(=黒字倒産)。
そのため、損益計算書・貸借対照表と同様に重要視されている表です。
期首、期中、期末のキャッシュ残高が分かるようになっているのでとても便利です。
2.財務諸表を作成後、計上漏れがないか確認する
財務諸表を作成した後は、必ず計上漏れがないか確認しなければなりません。
計上漏れの金額が多いと、経営陣・株主にマイナスな印象を与えます。
場合によっては、去年の決算内容と比べて計上漏れに気付く人もいるぐらいです。
なお、計上漏れがないか確認する方法は4つあります。
各事業部署に計上漏れがないか確かめる
まずやるべきことは、各事業部署に計上漏れがないか確かめることです。
特に営業部のような外出をしている時間が多い部署だと、交通費など申請していないことがよくあります。
経費の計上漏れがないように一斉メールを流しても、タイミングが合わずメールを確認していない人もいます。
それを防ぐためにも、各部の上長に計上漏れがないか呼び掛けてもらうことをお願いしてみてください。
筆者も決算準備をする前は、各部の上長に計上漏れの確認がないかお願いしていました。
過去の財務諸表と比べ、数字が乖離している部分がないか?
過去の財務諸表と比べながら、計上漏れがないか確認するのも大事です。
例えば、昨年度と比べて給料の額が半分以下になっていたら、おかしいと思いますよね。
また、売上が前年比の半分になっていたら何が原因なのか調べますよね。
各勘定科目の前年比を算出し、前年度100%から限りなく遠い(前年比と比べ50%以上離れているなど、基準を決めると良いです)勘定科目を中心に確認してみてください。
その結果、計上漏れも見つけやすくなるはずです。
仕訳・出納帳の内容を見て、計上漏れがないか確認する
日常的に記帳していた仕訳・出納帳の内容を見て、計上(転記)漏れがないか確認するのも重要です。
多くの会計システムでは仕訳を入力すれば出納帳・財務諸表に転記されますが、そうではないシステムもあります。
手書きで財務諸表に記入している企業も、計上漏れを起こしやすいので気を付けましょう。
3.経営陣、株主向けの決算資料を作成する
財務諸表の計上漏れがないことを確認したら、いよいよ決算資料を作成します。
決算資料を作成するときは、3つのことに気を付けましょう。
過去の株主総会で不評だった部分はないか?
決算資料の内容によっては、経営陣や株主に不満を持たれるケースがあります。
例えば「ページ数が多い」、「改行が少なくて文章が読みづらい」など、さまざまな視点から不満を持たれる場合も。
指摘されたにもかかわらず同じ過ちを起こすと、経営陣・株主からの信頼を失うので気を付けてください。
グラフや表を利用して、分かりやすく記載する
文章だけだと決算報告資料の内容が、複雑に見える恐れがあります。
そのため、グラフや表を利用して分かりやすく記載するのも重要です。
グラフだと、右肩上がり(右肩下がり)など、読んでいる側も理解しやすいです。
エクセルやワードのスキルを磨くと、効率的に資料作成できるので業務もラクに感じます。
難しい単語を使いすぎない
決算報告資料に、財務・会計の専門用語を使いすぎないのも大事です。
決算報告資料を読む人のなかには、経理・財務の知識がない人もいます。
高校生でも分かる内容を意識して作成すると良いでしょう。
だからと言って、幼稚な言葉を多用すると資料がみすぼらしく見えるので気を付けてください。
【株主向け】保有している企業の決算速報を見るには!?

読者のなかには、株式投資にハマっていて株主になってる人もいるでしょう(筆者もその中の一人です)。
そのときに大事なのが、いかに早く決算情報をつかむかです。
なぜなら、決算速報の前後は値動きが激しくなる可能性が高いからです。
決算情報を見ることができる場所はいくつかあります。
最後の章では、決算情報を見ることが可能な場所を紹介します。
1.自社のライブ映像を見る
リアルタイムで情報をつかみたい人は、ライブ映像を見ましょう。
自社・テレビ局のホームページ上の場合もあれば、YouTubeで放映しているケースもあります。
2.実際に会場へ足を運ぶ
株主総会の会場が近い場合は、会場まで直接足を運ぶのも一つの手です。
株主総会直前になると、株主向けに案内状が送付されます。
案内状を持っていくと会場内へ入れます。
企業によってはお菓子など土産を配っているところもありますね。
3.企業・証券会社のホームページで確認をする
企業・証券会社のホームページにも決算資料が載っています。
ただ、リアルタイムで情報を見ることはできないので、役には立たないかもしれません。
ちなみに、「IR情報」を選択すると財務諸表の閲覧ができます(ホームページによっては、IR情報と記載されていない場合もあります)。
※合わせて読みたい: 財務諸表の種類や見方、公開する理由を紹介!作成技術や分析能力を上げるためのコツとは?
4.日本経済新聞を購読する
日本経済新聞に、情報が載っているケースもあります。
とくに、大手企業だと掲載されている可能性も高いです。
また、現在は紙面ではなくスマホの画面で購読できるので、使い勝手も良く感じるでしょう。
まとめ
決算は、1年間の経営成績・財政状況を示すために行われる
決算は経営陣や株主に対して、1年間の経営成績・財政状況を示すために行われます。
決算報告の延期は、株主からの不信感を集めるため、株価が大暴落する場合も…。
株価を安定させるには、決算報告を延期しないのが大前提です。
決算報告資料を作成するには、財務諸表の知識が大事
決算報告資料には、ほとんどの場合「損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書」の財務諸表が載るので、見方を知っておくのは大事です。
財務諸表が読めるようになれば、企業がどんな状況か想像しやすくなり、株式投資をしている人にも役立つでしょう。
ほとんどの企業は、確定申告をしなければならないため決算報告は行われます。
ただ、数字に関することなのでウソを載せてはいけません(場合によっては粉飾決算として、刑事告訴される場合もあります)。
決算報告に携わる人は正しい知識を身に付け、効率的に業務を行ってくださいね!