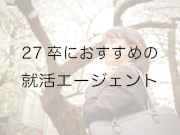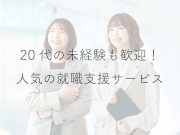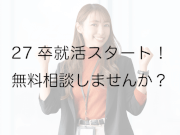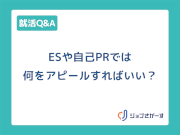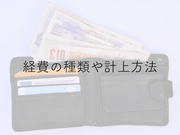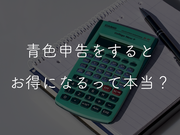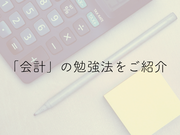Top > ライフ > 投資/株式/FX/仮想通貨
財務諸表の種類や見方、公開する理由を紹介!作成技術や分析能力を上げるためのコツとは?

日本だけではなく、世界各国で作成されています。銀行から融資を受ける際も必要になる資料です。
ただ、言葉は聞いたことがあっても、実際に財務諸表が何か分からない方もいるのではないでしょうか?
そこで今回は、経理職として働いた経験がある筆者が、財務諸表の概要や見方、読み解く能力を高めるコツをお教えします!
財務諸表の知識がないのに財務課への配属が決まった方。
株式投資など企業への投資を考えている方は、財務諸表の概要を理解して是非実務に役立ててください。
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】財務諸表の種類や見方、公開する理由を紹介!作成技術や分析能力を上げるためのコツとは?
財務諸表を作成するには「日商簿記2級・3級」の内容をマスターしよう!
財務諸表の分析をする場合は、日商簿記1級の学習をした方が良い
財務諸表とは一体何なのか?

財務諸表は端的に言うと、会社の決算状況を示した複数の書類です。
「一般社団法人・社会福祉法人・公益法人・学校法人・宗教法人」などいろいろな団体がありますが、ほとんどの団体は会計基準のルールに従って財務諸表を作成しています。
ただし、財務諸表は複式簿記で利用する書類なので、単一簿記で 確定申告 を行っている方は、財務諸表の作成義務はありません。
財務諸表は、大きく分けて3つの資料から成り立つ

この章からは、財務諸表の具体的な中身について見てみましょう。
今回は、最低限覚えていただきたい書類を3つ紹介します。
いわば、財務諸表の基礎といったところです。
ただ、財務諸表として実際に提出しなければならない書類は、会社の形態や売り上げ規模などによって変わるので、税務署や顧問税理士へ質問することをおすすめします。
①損益計算書
「損益計算書」は、確定申告時の納付額を決める際にメインとなる書類です。
損益計算書に記された「当期純利益」が多いほど、課税対象額も上がります。
企業の経営成績を示した表
損益計算書は、企業にかかった費用・収益のみを算出した表です。
費用とは「売上原価、販売費および一般管理費。営業外費用、特別損失」が挙げられます。
逆に、収益とは「売上高、営業外収益、特別利益」です。
これ以外の勘定科目は損益計算書では計上してはいけないことになっています。
なお、損益計算書の金額を計算する際は、下記の公式を覚えると便利です。
1.売上高-売上原価=売上総利益
2.売上総利益-販売費および一般管理費=営業利益
3.営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益
4.経常利益+特別利益-特別損失=税引前当期純利益
5.税引前当期純利益-法人税、住民税および事業税=当期純利益
計算の流れは、1番、2番の順で最後が5番です。
これさえ理解すれば、どの費用(収益)の金額が大きいか一目でわかるのでとても便利です。
損益計算書を分析するときのポイントとは?
ここでは、実際に損益計算書を分析するときの4つのポイントを紹介します。
・なぜ赤字になっているのか?
赤字になるのがいけないと思ってる方もいると思います。
しかし、赤字と言っても許されるモノから許されないモノまであります。
例えば、借入金の利息が莫大すぎて赤字になっているのであれば、黒字になるまでの見通しが遠いため危険です。
ただ、黒字を出すための赤字だったら多少印象も良くなります。
良い赤字か悪い赤字か見極めることを覚えましょう!
・黒字だからといって、100%良いわけでもない
黒字計上でも、キャッシュが手元にないと倒産する危険性もあります。
例えば、売上高が計上されていても、キャッシュを回収するのが数カ月後だったら、取引先への支払を滞らせる場合も。
その状況が起こると、手形の「不渡り」が発生します。
不渡りを連続で出すと、銀行口座が凍結されるため事業継続が難しくなります。
黒字企業だからといって安易に、安心するのはやめましょう。
・本業で儲けは出ているか?
何がメインで儲かっているか確認するのも大事。
例えば、営業利益が赤字なのに経常利益が黒字になっている場合は本業で儲けが出ていないので、事業計画を練り直した方が良いという結論に至ることが多いです。
特に、土地や株の評価益が黒字を担っている状態だとすれば危険です。
なぜなら、評価益は変動するから。
その年は評価益が出ていたとしても、翌年には評価損が発生する恐れもあります。
儲けの大半をどの勘定科目が占めているのか掴みましょうね!
・営業費用をかけすぎていないか?
営業費用と営業収益のバランスが良いか見るのも大事。
仮に、儲け額が少ないのに無駄な営業費用をたくさんかけると、会社の儲けも出づらいです。
特に、過去の損益計算書と比べて著しく営業費用の金額が上がっている場合は要注意。
急激な上がり方の場合、倒産する危険性もあるので気を付けましょう。
②貸借対照表
「貸借対照表」は、企業の業績について記載された表ではありませんが、損益計算書とセットで覚えておきましょう。
企業の財政状態を示した表
財政状態とは、企業が保有している「資産、負債、純資産」の金額が算出された表です。
資産は「流動資産、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産」。負債は「流動負債、固定負債」。資本は「株主資本、評価換算・差額等、新株予約権、少数株主持分」があります。
なお、貸借対照表の場合は「資産=負債+純資産」が公式です。
読み取ることができれば、企業の力が分かるでしょう。
貸借対照表を分析するときのポイントとは?
貸借対照表を分析するときのポイントを主に3つ紹介します。
・現金と借入金のバランス
借入金の額が返せそうな金額か見るのも大事です。
例えば、キャッシュが100万円に対して、借入金が1億円だとどうでしょう。
「返済は厳しい」と思いますよね?
つまり、キャッシュに対して借入金が多いほど、倒産リスクも高いと言えるのです。
・固定資産の所有具合
固定資産の所有を調べるのも大事です。
土地や車両運搬具などは、持っているだけで税金がかかるのでキャッシュが減る原因に。
また、固定資産はほとんどの場合「減価償却」されるため価値も下がります。
特にキャッシュが少ない状態で固定資産を大量に保有している場合は要注意です。
・株主配当金の金額
証券市場へ上場している場合は、株主配当金が発生しているか確認するのも重要。
株主へ還元できるということは、会社に余裕がある表れだと言っても過言ではありません。
年々、株主配当金の金額が上がっている場合は、企業に余裕が出てきている可能性は高いです。
③キャッシュフロー計算書
最後に紹介するのが「キャッシュフロー計算書」です。
キャッシュの状況を見る上で大切な書類です。
キャッシュの出入りを示した表
キャッシュフロー計算書は、お金の流れを示した表です。
主に「営業キャッシュフロー(販売費一般管理費など)」、「投資キャッシュフロー(固定資産の購入・売却など)」、「財務キャッシュフロー(キャッシュの借入・返金、配当金の支払いなど)」の3つの流れについて記載します。
その後、期首のキャッシュ残高を足せば、期末のキャッシュ残高が出る仕組みとなっています。
財務諸表を企業が作成する理由

財務諸表の作成作業は手間がかかりますが、ほとんどの企業で行っています。
この章では、財務諸表を企業が作成する理由について紹介します。
月、年度ごとの財政状態や経営成績などを把握する
財務諸表は、月、年度ごとの財政状態や経営成績を把握するために便利な書類です。
損益計算書の場合は「1カ月、3カ月、半年、1年」の4つのパターンで作成されるケースが多いでしょう。
昔は手書きで財務諸表をするのが当たり前でしたが、現在は会計ソフトを利用できるためデータ抽出する期間を設定できます。
特に、経営陣や株主へ企業の状況を説明する際に役立つでしょう。
確定申告の際に、財務諸表が必要となるから
財務諸表は確定申告時に必要になるので、作成する必要があります。
青色申告を行っている個人事業主・法人は財務諸表の提出義務が生じるため、財務諸表を作成しなければならないのです。
確定申告の締切日までに財務諸表の提出を行わないと、税務署から督促が来て「延滞税」、「重加算税」などが加算される原因となるので要注意です。
株主や経営陣などへ、企業の内部事情を知らせるため
財務諸表は、株主や経営陣などへ企業の内部事情を知らせる書類としても活躍します。
財務諸表を提示することで株主や経営陣から指摘されます。
指摘された内容を、できるだけ反映させながら予算編成に役立てるといった形です。
財務諸表を会社が公開した方が良い理由とは?

財務諸表をおおやけに公開しない企業もあります。
しかし、財務諸表はできるだけ見せた方が良いです。
この章では、財務諸表を公開するメリットを紹介します。
不正をしていないことのアピールへつながる
財務諸表を公開することで、不正をしていないアピールへつながります。
企業の財政状態や経営成績を財務諸表で示せば、勘定科目ごとに細かく数字が記録されているため、株主へ安心感を与えやすいです。
また、赤字や黒字になった理由を説明する際、財務諸表の金額を指しながら説明すると株主へ伝わりやすいので、企業への信頼度を落とさずに済むでしょう。
いくら口頭で理由を説明しても、根拠を示す財務諸表が作成されていないと説得力は低いですし、株主が企業へ対して不信感を抱く原因へつながります。
企業のブランド力を落とさないためにも、財務諸表は必要な書類なのです。
上場企業の場合は、財務諸表の結果が株価へ影響する
東証一部など、株式市場へ上場している企業の場合、財務諸表の結果によって株価へ影響します。
特に財務諸表がおおやけに発表された日は、株価の変動が激しくなるでしょう。
ただ、財務諸表で業績が悪いからと言って、株価が下がるとは限りません。
例えば、赤字だったとしても、株主の想定内であれば株価が上がる場合もありますし、逆に黒字だったとしても、株主の想定より悪い数字だと株価が下がる場合もあるので要注意です。
財務諸表の公開を延期すると、株価が暴落する場合もある
企業によっては、業績悪化により財務諸表の公開を延期する場合も。
例年、財務諸表を公開していた企業が財務諸表公開の延期をすると、株主からの信頼度を失います。
なぜなら「企業が何か悪いことをしているのでは?」と思う株主が増えるためです。
その結果、株を売却する方が増えて、暴落する原因になるのです。
財務諸表について勉強するには、どうすれば良い?

読者のなかには、財務諸表について勉強したいと思われた方もいると思います。
そこで最後の章では、財務諸表を学習するときのポイントを紹介します。
財務諸表を作成するには「日商簿記2級・3級」の内容をマスターしよう!
経理職などで財務諸表を作成しなければならない場合は、 日商簿記2級 ・ 日商簿記3級 の内容は最低限マスターしましょう。
この内容をマスターしなければ、財務諸表を作成するのは難しいです。
マスターする内容は大きく分けて3つで良いです。
1.仕訳のルールを覚える
財務諸表を作る前に、仕訳のルールを覚えるのは基本!
仕訳とは、取引内容を記録するための処理です。
左右に分けて勘定科目を記載する決まりで、左側に記載する内容を「借方」、右側に記載する内容を「貸方」と呼びます。
財務諸表を作成する上で、基礎になる内容なので要注意です。
2.勘定科目の種類を覚える
財務諸表では、勘定科目ごとに金額を記載します。
費用として発生した金額が、どの勘定科目に当てはまるか理解しておかないと、財務諸表をつくるときに苦労するので気を付けましょう。
なかには「○○費」と付いている勘定科目でも「資産」の勘定科目になる場合もあるので引っかかる場合も。
ただし、企業によって勘定科目の記載方法は違うので、臨機応変に対応してください。
3.財務諸表への反映方法を覚える
財務諸表への反映方法を覚えるのも大事です。
先述しましたが、損益計算書の場合は「費用」、「収益」の仕訳内容を。
貸借対照表の場合は「資産」、「負債」、「純資産」に該当する仕訳内容の金額を反映します。
例えば「(借方)費用×× (貸方)資産××」の仕訳の場合は借方の金額を損益計算書へ。
貸方の金額を貸借対照表へ反映させます。
ただし、財務諸表へ記載する金額は、計算後の数字なので要注意です。
財務諸表の分析をする場合は、日商簿記1級の学習をした方が良い
なかには、財務諸表の分析について深く勉強したい方もいるでしょう。
その場合は、 日商簿記1級 の学習をおすすめします。
1級は会計学などの法律論について学べますし、分析の際に使う公式をたくさん学ぶことも可能です。
また、日商簿記1級の取得ができれば、税理士試験の受験資格が与えられるなどメリットも多いでしょう。
まとめ
財務諸表は複数の書類をまとめた決算書類
財務諸表は1つの表だけではなく「損益計算書」、「貸借対照表」、「キャッシュフロー計算書」など複数種類の書類をまとめたものを指します。
ただし、会社の形態によって、提出する書類は違うので気を付けましょう!
財務諸表の作成は、ほとんどの企業で行われる
複式簿記での記帳を行っている企業だと財務諸表の作成義務があります。
経理職として働く場合は、財務諸表の作成方法は覚えておきましょう。
財務諸表は、企業の財政状態や経営成績を読み取る際に役立ちます。
ぜひ、数字に強くなって財務諸表の読み取り能力を身に着けてみてはいかがでしょうか?