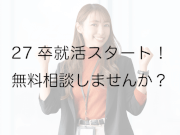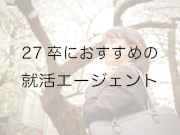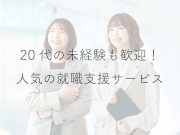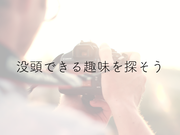日商簿記3級の試験日や合格率、難易度、問題パターン

簿記の基本知識を抑えたい方におすすめの資格で、10代から60代オーバーの方まで幅広い年代の人が受験しています。
簿記3級の資格取得のために、勉強時間を割いている方もいるでしょう。
しかし、自己流での問題の解き方や勉強方法が、時として裏目に出る場合も。
そこで今回は、学生時代簿記の勉強をしていた私が、試験合格率を上げるためのコツを紹介します。
難易度や解答時間など、日商簿記三級の概要も記載してあるので、簿記初心者の方は参考にしてみてください。
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】日商簿記3級の試験日や合格率、難易度、問題パターン
日商簿記三級の試験日、申し込み方法、試験時間、難易度、合格発表日は?
はじめに:日商簿記三級の概要を理解しよう!

日商簿記三級がどんな資格か詳しく見てみたいと思います。
取得すると、どう役立つのかも含めてご覧になって見てください。
日商簿記三級の主催元は?
日商簿記三級は「日本商工会議所」が主催している試験です。
日本商工会議所は「経済三団体」のうちの一つで国内で有名な団体です。
簿記資格のなかでもメジャーな資格と言っても良いでしょう。
ブランド力もあるため、資格取得すると進学や就職で有利になる場合もあります。
日商簿記三級の出題科目は?
出題科目は「商業簿記」に関する内容です。
商業簿記とは、一般的な企業で利用される簿記のことで、ほとんどの企業で利用されます。
例えば「商品を売り上げた」、「給料を支払った」など、企業の会計処理を行う際に必要な知識です。
なお、日商簿記三級は簿記初心者のための資格で、中小企業や個人商店など小規模企業での 経理 で役立ちます。
最終的に日商簿記一級、 二級 を取得したい方も、三級の内容が土台になるため理解しておきましょう。
日商簿記三級の試験日、申し込み方法、試験時間、難易度、合格発表日は?

ここからは、日商簿記三級に関する実施要項やデータについて見てみましょう。
日商簿記三級は、1年間に3回実施されるためチャンスが多いです。
2017年度は「6月11日、11月19日、(2018年)2月25日」に実施されます。
試験時間は120分で7割以上点数を取れば合格です。
なお、日商簿記一級から三級のなかで受験者が多い級が「三級」です。
1回の試験日で「10万人」前後の申し込みがあります。
申し込み方法は、商工会議所によって違うため注意です。
インターネットや商工会議所での申し込みが主流ですが、銀行振込で申し込めるケースもあります。
そのため、申し込む直前に商工会議所のホームページを見て、確認するのを忘れないようにしましょう。
また、第138回~146回のなかで、一番合格率が高かったのが第139回の「54.1%」、逆に合格率が低かったのは第141回の「26.1%」です。
受験実施日によって合格率に差があります。
マイナーな場所から出題されると、不合格者増加の傾向が強くなるでしょう。
合格発表日や発表方法も、商工会議所によって違います。
インターネット上の場合もあれば、商工会議所へ行って知る合否を知るケースもあるので調べておきましょうね。
日商簿記三級の大まかな問題形式は決まっている

例年通りにいけば、大問が5問出題されます。
この章では出題パターンについて、詳しく説明します。
第1問は仕訳問題が出題される!
1問目は仕訳問題が5問出題されます。
全て正解すれば、20点です。
仕訳については、過去問と同じような内容が出題されることもあるので要注意。
また、仕入・売上の仕訳では「三分法」と「分記法」の2パターンありますが、三分法で出題されるケースがほとんどです。
三分法とは「仕入、繰越商品、売上」の3つの勘定科目を用いて仕訳するパターンです。
例を見てみましょう。
例1.商品500円分を仕入れ、代金は掛けで支払った
(借方)仕入500(貸方)買掛金500
商品を仕入れたときには「仕入」勘定を利用します。
なお、分記法のときは仕入が「商品」勘定に変わるので要注意です。
例2.商品を400円でA商店へ販売し、代金は掛けとした
(借方)売掛金400(貸方)売上400
商品を売り上げたときには「売上」勘定を利用します。
この場合も、分記法のときは売上が「商品」勘定に変わるので要注意です。
例3.2017年度の期首商品棚卸高300円で、期末商品棚卸高が500円だった
(借方)仕入300(貸方)繰越商品300…①
(借方)繰越商品500(貸方)仕入500…②
①は、前期分に残っていた商品を当期分の売上原価に組み入れる仕訳です。
つまり、2016年度に商品を仕入れたが、前年度に商品が300円分余ったので、2017年度の売上原価に回したというイメージをすると良いでしょう。
②は当期に商品を仕入れたが、商品が500円分残ったので、2017年度の売上原価から控除する(=2018年度の売上原価に回す)ための仕訳です。
精算表や財務諸表の問題でも頻繁に出題されるので覚えておきましょう。
なお、分記法の場合は「仕入」勘定を使わないため、この仕訳は発生しません。
「消耗品費」と「消耗品」勘定にも気を付けよう!
勘定科目のなかには「消耗品費」と「消耗品」と言うようにややこしいものもあります。
消耗品費は「費用」ですが、消耗品は「資産」です。
しかも、消耗品の購入時も「消耗品費」で計上する場合と「消耗品」で計上するパターンがあるので注意しましょう。
第2問は、帳簿を記入する問題が出題される確率が高い!
2問目は、帳簿を記入するパターンが多いです。
帳簿には、下記のタイプがあります。
・商品有高帳
・売掛金元帳
・買掛金元帳
・支払手形記入帳
・受取手形記入帳
・当座預金出納帳
・総勘定元帳
上記帳簿のなかから出題される確率が高いでしょう。
帳簿の問題以外では、勘定記入の問題が出る場合も。
減価償却の処理方法などを確認しましょう。
ただ、この章の配点は10点前後と少ないため、苦手な問題だったら後回しするのも一つの手です。
第3問は、試算表の問題が出る確率が高い!
3問目は試算表の問題が出る確率が高いでしょう。
この章だけで、30点前後の配当があるため、絶対に解きたい場所です。
試算表には「合計試算表、残高試算表、合計残高試算表」の3種類あります。
ここで抑えておきたいのは金額の記入方法です。
合計試算表では、借方と貸方で発生した金額をそれぞれに記入しますが、残高試算表では「借方or貸方」の一方にしか入力しません。
例えば「現金」勘定で期中の借方金額が100円、貸方金額が70円だったとします。
合計試算表の場合は、借方に100円、貸方に70円と記入しますが、残高試算表では借方と貸方の差分を記入するルールです。
すなわち、借方の方が30円多い(100円-70円)ため、借方の欄にのみ30と記入します。
ただ、ごく稀に試算表の問題が出ずに、財務諸表の問題が出るパターンもあるので要注意です。
第4問は、伝票に関する問題が出題される可能性が高い!
伝票会計の問題が出る確率が高いです。
伝票には「入金、出金、振替、売上、仕入」の5種類あります。
伝票が虫食いになっていて、その中に金額や勘定科目を記入するパターンが多いでしょう。
出題パターンも、複雑ではないため過去問をやれば解けるはずです。
ただ、伝票会計ではなく、決算・訂正仕訳や単語の穴埋め問題、勘定記入が出題される場合もあります。
この章の配点も10点前後なので後回しにして良いでしょう。
第5問は、精算表or財務諸表の問題が多い!
5問目は、精算表や財務諸表の問題が出題されやすいです。
これは、1年間の取引内容を全て記入し完成させる問題です。
表が虫食いになっているので、その箇所に勘定科目や金額を記入します。
決算整理仕訳や修正仕訳が多いので、どれだけスピーディーに解けるかがカギとなるでしょう。
仮に全て解けなくても部分点が設定してあるので、たくさん解けば得点稼ぎができます。
なお、決算整理仕訳や修正仕訳で出題されやすいのは下記のパターンです。
・期首商品棚卸高と期末商品棚卸高の処理
・貸倒引当金の設定
・減価償却の処理
・前払、前受、未収、未払の計上
・仮払金、現金過不足の処理
・有価証券の売却
配点は30点前後あるので、避けて通るのは難しいです。
最低でも30分~40分は時間をとった方が良いでしょう。
試験問題は、実際にどう解けばよいの?

ここからは、試験問題の解き方について紹介します。
解き方を意識して、合格率を上げましょう!
第1問から順に解かない
解答用紙が配布され、第1問から順番に解く人もいるのではないでしょうか?
しかし、それはマズいです。
なぜなら、序盤で解く時間をかけた結果、第5問までいかない可能性があるからです。
前章でお伝えしましたが、第5問の配当は30点前後あります。
合格基準は全体の7割です。
つまり、第5問を1つも解かなければ不合格になる確率が一気に上がります。
それを防ぐために、配点が高い「第3問」と「第5問」を解けるだけ記入して、その後「第1問」、最後に「第2問」と「第4問」を解きましょう。
配当が大きい問題から解くのが基本です。
金額の書き方に気を付ける
数字の前に「¥」を付けたり、数字の後に「円」を付けると間違いです。
例えば、解答が1000円の場合は「1,000」と書きます。
「¥1,000」や「1,000円」は間違いになるため注意しましょう。
見直すポイントを決めておく
解答を見直すときは、何を見るか決めるのも大事です。
そうしないと、無駄な時間を使ってしまいます。
要チェックしていただきたい内容は主に4カ所です。
・記入漏れがないか?(名前を書いているか見る)
・解答の場所がズレていないか?
・単位が合っているか?
・誤答がないか?
上記4つを見直すと、得点率も上がるはずです。
また、見直す際も「これは合っている」という思い込みを捨て「どこか間違いがないか?」と疑問の気持ちを持つと良いでしょう。
その結果、間違っている箇所を見つけやすくなります。
冷静な気持ちになる
冷静な気持ちになるのも大事です。
理性より感情が勝ると、普段解ける問題でも解けなくなり、誤答が増える原因につながる恐れも。
試験最中に「100点満点をとったらどうしよう」とか、「試験が終わったら何しよう」とか、関係ないことをイメージするのは辞めましょう。
勉強の仕方で合格できるかが決まる!

この章からは、合格率を上げるための勉強方法について紹介します。
順序を守って勉強しましょう!
ステップ1.教科書を利用し、基礎的内容を覚える
日商簿記三級受験者のほとんどは、簿記初心者だと思います。
最初は、教科書を使い基礎的内容を覚えましょう。
基本を抑えなければ、日商簿記三級の合格は難しいですし、今後一級、二級を取るのも難しくなります。
教科書の内容が一通り理解できれば、日商簿記三級の勉強も捗るでしょう。
ステップ2.仕訳問題をたくさん解く
基礎的内容を理解した後は、仕訳問題をひたすら解きましょう。
理由は、簿記の基本は「仕訳」にあるからです。
さきほど、第1問で仕訳問題が出ると言いましたが、それ以外の問いでも仕訳は必要となります。
精算表や財務諸表の作成、勘定作成や帳簿記入など仕訳問題以外でも必要です。
つまり、仕訳ができないと得点を取るのも「難しい」のです。
仕訳専用の問題集を使い練習しましょう。
ただ、仕訳問題も効率的に勉強するにはいくつかのコツがあります。
1.初回は一通り解いてみる
初めに、仕訳問題を一通り解く理由としては、自分が苦手な場所を把握するためです。
手形、借入金、前払計上など、苦手な場所は人によってさまざまです。
得意な場所を、いくら勉強したからと言って、点数は伸びません。
1つでも苦手な場所を減らすことで、点数が伸びるのです。
また、問題を解く際も問題集に直接書き込むのではなく、ノートに解答を書きましょう。
すると、同じ問題内容を何度も解けるのでおすすめです。
2.解けなかった場所は、教科書を見直す
解けなかった場所については、教科書を見直しましょう。
解答の内容を覚えようとする方もいますが危険です。
理由は、出題パターンや金額が変わっただけで、解けなくなるケースがあるからです。
それを防ぐためにも、基本に返って教科書を見直すことは重要。
自分が「なぜ間違ったのか?」理由を知れば、次からはそこを意識し出し間違う確率が下がるはずですよ。
3.間違った問題のみ再度解く
再度仕訳問題を解く際も、間違った問題のみ解きましょう。
再度一通り仕訳問題を解こうとすると時間がかかり、別の勉強ができなくなることも。
効率的に解くためにも、間違った問題のみ再チャレンジする形式をとりましょう。
回を重ねるうちに、解く問題数も減っていくので、モチベーションを上げるという意味でも効果的です。
ステップ3.模擬試験を解く
仕訳問題を一通り解けたら、模擬試験を解きましょう。
人によっては、過去問をいきなり解き始める人もいますが、私はおすすめしません。
理由は、模擬試験の方が過去問より難しいケースが多いためです。
最初に難しい問題から解けば、その分たくさんの知識が身に付きます。
そのため、過去問を解くと高得点が期待でき、自分に自信を付けられます。
逆に、過去問を一通り解いた後に模擬試験を解くと、問題の難易度が上がったと感じ、人によっては自信を失い、日商簿記三級の勉強を辞めてしまう方もいるでしょう。
途中で勉強を辞めると、今まで勉強にかけた時間や労力が無駄になります。
また、模擬試験を解く際は、3つのことを守りましょう。
1.時間を測って問題を解く
問題を解く際は、時間を測りましょう。
時間を測ることで、本番と同様の雰囲気を味わえるので、緊張感が生まれます。
また、全ての問題を解き終えた時間を認識すれば、自分の現状を知ることも可能です。
スピーディーに解くかも試験で合格するコツなので、覚えておきましょう。
2.間違った場所を理解する
さきほども話したように、いかに間違った場所を減らすかが得点を稼ぐコツです。
間違った問題をスルーしたい気持ちも分かりますが、得点を伸ばすなら時間をかけてでも理解しましょう。
ただ、なかには理解しきれない場合もあると思います。
その場合は、解説を見ながら自分で再度解くのも有効。
すると、身体に染み付き問題が解けるはずです。
3.最終的には、解く時間を減らしていく
模擬試験を解く中で、解く時間を減らすのも大事です。
問題パターンは似ているので、何度も解けばコツをつかめるため、自然と解答時間も減ります。
なぜ解く時間を減らすのが大事かと言うと、「見直しの時間を多くとれる」からです。
ケアレスミスに気付く機会ができるため、合格する確率も上がります。
また、見直し時間を確保せず、時間いっぱいの状態で問題を解くと「焦り」が生まれる原因に。
ケアレスミスを引き起こす確率も上がります。
それを防ぐにも、解く時間を減らしておきたいです。
「短時間で解ける=ココロに余裕が生まれる=解答ミスが減る」という関係性を理解すれば、自然と正答率も上がるでしょう。
ステップ4.苦手な問題をひたすら解く
模擬試験を10パターン以上解いたら、そのなかから低得点だったものを抽出します。
苦手な問題を克服するためにも、低得点だった模擬試験を再度解くのは重要です。
間違った箇所をしっかり理解すれば、1回目より2回目の方が得点も高いはずです。
ちなみに私は、85点を超えたものについては高得点、85点以下を低得点に分類していました。
苦手な問題を何度も解くことで、全ての模擬試験で85点以上をとれるようにするのです。
苦手な問題も減り自分に自信が付くでしょう。
ステップ5.模擬試験と過去問を繰り返し解く
試験1カ月前になったら、模擬試験と過去問を繰り返し解きましょう。
この際、模擬試験はどのバージョンの問題でもOKです。
自分に自信を付けたければ、得意分野の問題を解いても良いですし、苦手な問題を減らしたければ難しい問題を解いても良いでしょう。
ただ、この段階は最終仕上げなので「モチベーションを落とさない」仕組みをつくることが大事です。
試験直前で、自信を失ってしまっては元も子もありません。
人によっては、ここで手を抜く人もいるので、毎日問題を解き続けましょう。
モチベーションを上げるために、好きな音楽をかけたり、受験終了後に何をしたいか考えたりすると良いです。
この段階で、試験問題を1時間以内に解ければ、合格する確率も高いでしょう。
日商簿記三級を勉強する人向けにおすすめの問題集

最後に、日商簿記三級を勉強する人におすすめする問題集を紹介します。
おすすめは「tac」から販売されている問題集です。
理由は、図面が入っておりテキストの内容が分かりやすいためです。
基本的知識を身に付けるために「 みんなが欲しかった簿記の教科書 」と「 みんなが欲しかった簿記の問題集 」は購入すると良いでしょう。
この2冊の内容をマスターした後に模擬試験を解くと最高です。
なお、模擬試験集は「tac」以外に「 資格の大原 」などいろいろな出版社から販売されているので「amazon」を利用し、何種類か取りそろえると良いでしょう。
pdfからダウンロードできるものもあるので使ってみてはどうでしょうか?
まとめ
合格率を上げるには仕訳を極めよう!
仕訳を極めれば合格率は自然と上がります。
完全マスターするつもりで勉強しましょう。
独学で勉強するなら、模擬試験を何度も解こう!
模擬試験は過去問と同じ形式で作成されています。
しかも、過去問よりも難しく作成されているケースが多いです。
よって、模擬試験を極めれば、過去問が簡単に感じる確率が上がり自信が付くでしょう。
問題の解き方と勉強方法で、日商簿記三級に合格するかが決まります。
ぜひ、勉強時間を確保して、試験日まで努力してみてはどうでしょうか?