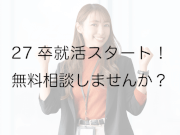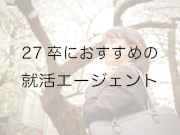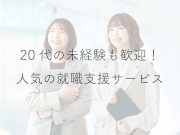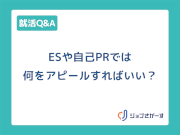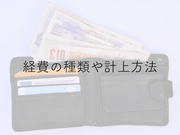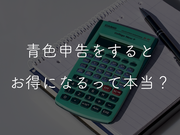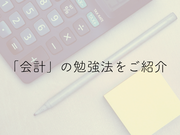日商簿記2級の難易度や試験日、問題の解き方や勉強方法を紹介!

それは「日商簿記2級」です。
この資格を持っていれば、転職活動や進学が有利になるケースもあります。
筆者も、学生時代に日商簿記2級を取得し、大いに役立っています。
合格するには、難易度や試験の問題範囲を知り、効率良く勉強をすることが大事です。
本記事では試験の概要だけではなく、受験に合格するためのコツも記載してあります。
日商簿記二級の概要を知り独学での合格を目指してみませんか?
資格取得で人生が変わるかもしれませんよ!
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】日商簿記2級の難易度や試験日、問題の解き方や勉強方法を紹介!
日商簿記2級の概要

まず初めに、日商簿記2級の概要を見てみましょう。
どういう資格なのか、理解していただけると幸いです。
そもそも日商簿記2級とは?
日商簿記2級は「日本商工会議所」主催で行われる検定試験です。
全国的にも知名度があるため、取得すると進学や就職活動で有利になる場合もあります。
また、社会人のなかには独学で勉強をして合格する方もいるため、誰にでもチャンスがあると言っても良いでしょう。
試験日程、料金
試験実施日は年3回あります。
2017年度については「(2017年)6月11日」、「(2017年)11月19日」、「(2018年)2月25日」で料金は4630円です。
申し込み方法は、主に商工会議所の窓口、インターネット申し込み、銀行振込の3パターンありますが、商工会議所によっては1パターンしか使えない場合も。
また、申し込み締切日も商工会議所によって違います。
場合によっては、申し込み方法が年度によって変わるケースもあるので、早めの確認をおすすめします。
試験科目、問題形式
試験科目は「商業簿記」と「工業簿記(原価計算含む)」の2科目です。
商業簿記とは、一般的な企業で会計処理をするときに必要な知識です。
お金の借入をした、自社株を売却したなど多くの企業で使われます。
一方の工業簿記は、製造業や工場がメインです。
主に、製品にかかったコストを算出する際に利用されます。
そのため、企業によっては使わないケースも。
しかし、日商簿記2級を取得するには工業簿記の知識も覚えておかなければ合格できません。
また、問題形式は大問が5問設定されています。
1~3問目は商業簿記に関する問題、4、5問目は工業簿記に関する問題というのが基本的な形です。
解答時間は2時間で70%以上の正答率(得点を得れば)で合格です。
なお、問題の出題傾向については、別の章で詳しく見ていきます。
合格率
合格率は、試験実施日によって多少のバラつきがあります。
平成29年6月11日に実施された試験から、過去9回の試験で合格率が一番高かったのは「47.5%」、低かったのは「11.8%」です。
今まで日商簿記2級で出題されていない問題内容だったり、模擬試験であまり注目されていない問題が出題された場合、合格率が下がる傾向にあります。
また、出題範囲も頻繁に改定されます。
特に新しく追加された箇所は勉強した方が良いでしょう。
簿記二級の問題を細かく見てみよう!

この章からは、実際に問題の概要を細かく見ていきます。
大よそのパターンは決まっているので、理解して勉強に生かしましょう!
1問目の出題内容(配当20点)
第1問は仕訳問題が5問出題されます。
仕訳1問につき、1~2分の時間を割きトータル10分で解くのが理想です。
ただ、仕訳と言っても難しい問題が出る場合もあります。
注意していただきたいのは下記に関する仕訳です。
本支店会計
これは本店や支店のやりとりを仕訳する問題です。
例を見てみましょう。
例.A支店にA支店負担の水道光熱費〇〇円をB支店が立替払いしたとの連絡が来た(当社は支店独立計算制度を採用している)
解答は (借方)水道光熱費○○円 (貸方)B支店○○円 となります。
この問題では、どの支店の仕訳をしているか見極めるのが重要です。
今回は、A支店に連絡が来たと問題文に記入してあるので、A支店で発生した仕訳を解答しなければなりません。
仮に、B支店の仕訳を記入する問題だと「(借方)A支店○○円 (貸方)現金○○円」が解答です。
出題内容が「本店にA支店負担の水道光熱費〇〇円をB支店が立替払いしたとの連絡が来た」だと、本店の仕訳内容を記入しなければなりません。
この場合、本店は取引に絡んでいないので仕訳の解答は「仕訳不要」が正解です。
仕訳問題では、たまに「仕訳不要」と記入させる問題が出題されるので、引っかからないようにしましょう。
手形
手形にまつわる仕訳問題も、出題されることが多いです。
手形には「受取手形」と「支払手形」の2種類があります。
受取手形とは、売上を回収するために使われる手形、支払手形とは、取引先へ支払う際に使われる手形です。
ただ、手形の流れにもいろいろなパターンがあります。
例えば、手形に記載されている金額を割り引いて入金されるケースもあれば、受け取る予定だった手形を他の取引先へ渡したりなど、多くのケースが考えられます。
日商簿記2級では、手形に関する仕訳が出る確率も高いので、教科書やテキストを使い手形の流れをマスターしましょう!
繰延資産
繰延資産には「開業費、開発費、創立費、株式交付費」などがあります。
なぜ注意すべきかと言えば、償却年数が勘定科目によって違うためです。
例えば、開業費は償却期間5年ですが、株式交付費の場合は3年というように、勘定科目によって異なります。
頭が混乱する方もいるので、勘定科目ごとに償却年数を覚えましょう。
固定資産の評価、売却、除却
固定資産を手放す仕訳の問題のときも要注意です。
例えば、問題文に「固定資産を売却した」と書いてあれば「固定資産売却損」を使いますが「除却した」場合は「固定資産除却損」です。
過去問や模擬試験では、固定資産売却損を使った仕訳をする機会が多いため、除却なのに固定資産売却損と記入する人もいます。
売却と除却を書き間違えただけで点数を失うのはもったいないので気を付けましょう。
「あと一問正解しておけば…」という状態にならないためにも、仕訳は全問正解を目指したいところです。
2問目の出題内容(配当20点)
第2問は、伝票会計or表を作成する問題の場合が多いです。
伝票会計が出題されれば、決まったパターンで出題されることが多いため、高得点が期待できるでしょう。
ただし、表の作成問題だと厄介です。
ここでいう表とは「株主資本等変動計算書、銀行勘定調整表、その他の帳簿」を指します。
実施回によっては、馴染みが少ない問題が出題され大量に点数を落とす場合も。
難易度が高い問題だったら、一番最後に回す手もアリです!
第2問でかける時間は20分が理想です。
3問目の出題内容(配当20点)
第3問では、財務諸表作成or精算表作成のパターンが多いです。
財務諸表には、資産・負債・純資産勘定の金額を集計した「貸借対照表」、負債・収益の金額を集計した「損益計算書」、お金の出入りを示した「キャッシュフロー計算書」の3つあります。
表の所々に空欄があるので、数字を埋めていく形です。
なお、ここで重要なのは分かる箇所からどんどん記入することです。
第3問目では、決算整理事項や修正仕訳を解きながら数字を記入していきます。
しかし、なかには解けない仕訳が出てくる場合も。
解けない場合は別の仕訳へ移り、テンポ良く数字を記入するのが大事です。
また、解けなかった部分が採点箇所に入らないケースもあります。
場合によっては、仕訳が分からなくても、足し引きで解けるケースもあるので落ち着くことが大事です。
いかに空欄を減らすかが合格率を上げる近道となります。
なお、第3問でかける時間は30分が理想です。
4問目の出題内容(配当20点)
第4問からは、工業簿記の問題に入ります。
なお、商業簿記のようにどういう問題パターンかと予想するのは難しいです。
ただ「費目別計算」の出題確率は比較的高いでしょう。
費目別計算とは、製品にかかったコストを費目別に計算する方法を指します。
製品原価は、主に「材料費」、「労務費」、「経費」の3つから成り立ちます。
この3つの費用は、さらに「直接費」と「間接費」に分かれます。
つまり「直接材料費」、「間接材料費」、「直接労務費」、「間接労務費」、「直接経費」、「間接経費」の6つに分かれるということです。
「直接費と間接費の金額を求めよ」、「材料費、労務費、経費を直接費と間接費に分けて求めよ」と出題されるケースもあります。
ただし、費目別計算の問題は出ずに個別原価計算など、全く違うパターンで出題されることもあるので要注意です。
第4問でかける時間は20分が理想です。
5問目の出題内容(配当20点)
第5問では、原価計算に関する問題が出題されやすいです。
原価計算には、下記パターンがあります。
- 個別原価計算
- 総合原価計算
- 標準原価計算
- 直接原価計算
なお、個別原価計算においては「単純、等級別、工程別」と複数パターンがあります。
さらに、問題が難しくなると応用問題を出題してくるケースもあるため、日頃から難易度が高い模擬試験を解くのも大事です。
解答時間は20分が理想です。
簿記二級の試験の解き方

それでは、実際に試験を解く際のコツを紹介します。
問題を解くコツを覚えれば、合格できる確率も上がるので参考にしてみてください!
問題を一通り見る
問題用紙が配布されたら、まずは問題を一通り見ましょう。
自分が苦手そうな問題や、時間がかかりそうな問題を把握できます。
その際、問題用紙に自分が苦手そうな問いにマークを付けると良いでしょう。
すると、試験を解いてる最中も「これは苦手な問題だ」と冷静に判断することが可能です。
最初のほうでいきなり分からない問題を解こうとすると、途中でパニックになり脳内がフリーズする原因になり、集中力が最後まで持たない場合も。
試験開始の段階で全ての問題を目に通すと、問題の大枠を把握できるので試験中に慌てることも減るはずです。
分かる問題から解く
分からない問題は後回しにして、分かる問題を解くのも大事です。
試験には7割以上点数をとれば合格します。
日商簿記2級の得点配当は、商業簿記が6割(60点分)、工業簿記が4割(40点分)です。
極端な話、工業簿記が苦手な人でも商業簿記で60点取れば工業簿記は10点以上で合格です。
逆に商業簿記が苦手な方も、工業簿記で40点取れば、商業簿記では30点以上取るだけなので、自分の得意科目から攻めることは重要だと言えるでしょう。
前半は分かる問題から解いていき良い流れをつくる。
後半は苦手だったり分からない問題を埋める方法にすると、合格率も必然的に上がるはずです。
無理難題な問題に挑むのを最後にとっておけば、試験へ対するモチベーションが維持される時間も長くなるので、効率良く得点稼ぎができるでしょう。
見直し時間は最低20分とる
見直し時間も、もちろんとる必要があり最低20分は大事だと思います。
私がおすすめする見直し順は下記の通りです。
- 名前の記入
- 解答の場所・方法が合っているか?
- 適当に数字を記入した箇所の見直し
名前の記入は絶対確認しましょう。
全て正解していても、不合格になります。
冷静さを失っている方に多く見られるので大事です。
解答の場所・方法も確認することを忘れてはなりません。
よくあるのは、解答を記入する場所が1つずつズレているということです。
正しい解き方をしても、不合格になってしまいます。
また、単位を間違って答える人もいます。
例えば「単位:万円」で答えよと指名されているのに、「単位:千円」で答えるケースです。
数字の桁数を間違って、不合格になる人もいるため注意しましょう。
2つのことが終わったら、分からなかった箇所や適当に解いた箇所の見直しへ移ってください。
もしかすると、閃いて正しい解き方が思い浮かぶかもしれません。
100点満点でも、70点でも結果は同じです。
1つの問題に時間を割くのではなく、全ての問題に時間を割きましょう。
日商簿記2級に受かるための勉強方法

この章からは、実際に日商簿記2級に受かるための勉強方法について紹介します。
今から紹介する5つのポイントを意識すれば、結果も出やすくなるので試してみてください。
1.仕訳は完璧に抑える
仕訳は完璧に抑えましょう。
第1問の仕訳問題を満点とるというのも大きな理由ですが、もう1つ大事な理由があります。
それは、ほとんどの問題で仕訳がからんでいるということです。
例えば、第3問の財務諸表や精算表の問題では、決算整理事項などで仕訳が必要になりますし、工業簿記においても仕訳が必要となります。
すなわち、簿記の基本は「仕訳」だということです。
仕訳を覚えれば、大半の試験問題は解けるでしょう。
2.模擬試験を解いた後に過去問を解く
模擬試験を解いた後に、過去問を解くのも効果的。
理由は、過去問よりも模擬試験の方が難易度が高い場合が多いためです。
難易度が高い問題を解いた後に、簡単な問題(過去問)を解くと本番でも受かる自信が付きます。
理想は試験3カ月前から模擬試験を解き始め、試験2カ月前から模擬試験と過去問をミックスして解く形です。
いろいろな種類の問題パターンや解き方が頭の中に入り、試験に活きるはずです!
3.模擬試験や過去問は同じ問題を何度も解く
模擬試験や過去問は、1回解くだけでは頭の中に入りづらいです。
そのため、同じ問題を何度も解くことが重要。
同じ問題を解くと、問題や解き方のパターンを覚えられるので合格基準点に達する確率も上がります。
その結果、自分の自信につながり勉強をし続けるモチベーションを維持する効果も期待できます。
なお、問題を解く際は、テキストに解答を直接書き込まず「ノートorコピーした解答用紙」に記入しましょう。
すると、テキストを何度も使用できるためおすすめです。
4.複数種類の問題テキストを購入する
複数種類の問題テキストを購入するのも大事です。
出版社によって、模擬試験集の問題設定方法は違います。
標準的な難易度で仕上げている場合もあれば、難しさMAXの問題までさまざまな種類の問題集があります。
一概に簿記の模擬試験集と言っても、問題のタイプが異なるケースも多いのです。
いろいろな出版社の模擬問題を解けば、いろいろなパターンの問題を解くことで、本試験で同じパターンの問題が出題される可能性も高くなります。
最近ではpdfでダウンロードできるタイプや無料でもらえるテキストもあるので、使ってみてはどうでしょうか?
5.分からない問題があれば、教科書や解説を見て理解する
模擬試験や過去問を解いて、分からなかった部分を放置するのはもったいないです。
教科書や解答の解説を見て理解しましょう。
分からないままにすると、本試験でとんでもない目に遭う場合も。
試験によっては、あなたの苦手な項目しか出題されず、不合格になるケースもあるのです。
また、分からない箇所を理解する際は解答を覚えるのではなく「なぜこの答えになるのか?」とプロセスを理解するのが大事。
分からない問題を理解するのは、正直時間がかかります。
しかし、確実に試験で点数を取るには、苦手な箇所を1つでも減らすのが一番の近道なのです。
独学(我流)で簿記の勉強することに限界を感じたら…

独学での日商簿記2級の勉強が、限界だと感じたら何かに頼るのも大事です。
そこで最後に、勉強方法を3つ紹介するので参考にしてみてください。
1.簿記の知識がある友人に指導してもらう
お金がかからずに済むのは、簿記の知識を持っている友人に付き合ってもらうことです。
問題の解き方や簿記の基礎知識を教えてもらえば、合格率も高くなります。
例えば、日商簿記2級を持っている友人や、経済学部で簿記の勉強をした人、さらに会社内の経理課で働いている人など、探せばいくらでもいます。
友人から無料で教わるのは気が引ける場合は、食事をおごるとか少しお礼をすると良いでしょう。
すると、教えている側も気分が良くなり、あなたに有益なことを話してくれるかもしれませんね。
2.通信講座を申し込む
通信講座を申し込むのも一つの手です。
我流での勉強方法は上手くいかないけど、自宅で勉強を頑張りたい人におすすめです。
主婦や会社員など、日常生活が忙しい方に需要があります。
テキストは、3万円台から5万円台のものが多いです。
問題の解き方が詳しく記載してあったり、絵が入り分かりやすいテキストだったりと工夫されています。
また、電話やメールで質問できるサービスを設けているところもあるので、安心して勉強できるでしょう。
3.専門学校へ通いながら勉強をする
専門学校で勉強する手もあります。
実際に、講師が目の前で授業するパターンであれば、分からない箇所をすぐに質問できるので、短時間で解決できます。
また、クラスメイトもいるため、お互い励まし合ったり勉強し合ったりモチベーションの維持にも役立つでしょう。
ただし、授業料は10万円を超えるケースがほとんどなので、金銭的な余裕が必要です。
有名どころでは「 資格の大原 」や「 tac 」などがあります。
興味がある方は説明会へ行くのも一つの手です。
まとめ
簿記を制するには仕訳から
商業簿記、工業簿記の両方とも、仕訳を切れないと解けない問題は山のようにあります。
普段の勉強でも、仕訳問題はたくさん解きましょう!
模擬試験や過去問は何度も解く
同じ問題を何度も解き、間違った箇所を理解すれば分からない問題は減ります。
ただし、問題を解く際は「模擬試験」を何度も解いた後に「過去問」を解きましょう。
順序が逆だと、難易度が高く感じモチベーションが下がる確率が高くなるので要注意です。
日商簿記2級は、東京や大阪など全国各地で行われています。
資格は持っていて損をすることはほとんどありません。
ぜひ、経理職を目指している方は日商簿記2級を取ってみてはどうでしょうか!?
※本記事に掲載されている内容などは2017年9月10日現在の内容です。問題の形式が変わる場合もあるのでご注意ください。