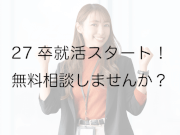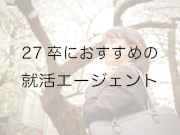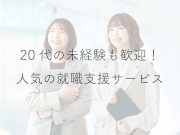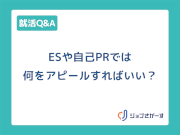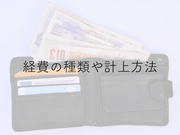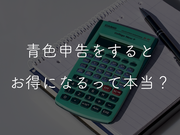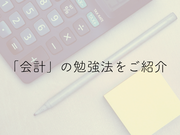「弊害」の意味と適切な使い方!言い回しや例文を覚えてビジネスシーンで使いこなそう

特にビジネスシーンにおいて、大きなプロジェクトを進行するときには、物事のメリットとデメリットを踏まえて「弊害が生じる」「弊害が伴う」などと使うかもしれません。
「害」という文字が示すように、少しマイナスなニュアンスを伝える時に使う言葉ですが、意味を正しく理解し、使いこなせていますか?
今回は「弊害」の言葉の意味と適切な使い方を、例文を交えながら解説します。
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
「弊害」の意味

「弊害」は「へいがい」と読みます。
「害になること。他に悪い影響を与える物事。害悪。」を意味します。
稀に「併害」と誤って認識されることがあるため注意しましょう。
「併害」という言葉はありません。
「弊害」の基本的な例文

「弊害」は、その単語のみで使われることは少なく、決まった言い回しがあります。
以下で代表的な「弊害」を使った例文を紹介します。
「弊害を伴う」
例文:「このシステムを使うと効率が上がり人件費削減になるが、導入費用が高いという弊害を伴います。」
「弊害を生じる」
例文:「都市開発は、人々にとっては便利だが、環境にとっては様々な弊害が生じている。」
「弊害がある」
例文:「就寝前のスマートフォンの使用は、睡眠に弊害があると言われている。」
「弊害をもたらす」
例文:「大幅な人員削減は、会社に弊害をもたらすだろう。」
「弊害を及ぼす」
例文:「未成年の喫煙は健康に多大な弊害を及ぼす。」
「弊害」と「障害」「支障」の違い

「障害」との違い
「障害」は「しょうがい」と読み、「正常な進行や活動の妨げとなるもの。」を意味します。
「障害」は「妨げとなる」という意味を持ちますが、「弊害」と違い「害をもたらす」という意味はありません。
「支障」との違い
「支障」は「ししょう」と読み、「事をなす妨げとなる物事のこと。差し障りがあること、物事の妨げになること。」を意味します。
こちらも「障害」と同様、「弊害」のように「害をもたらす」という意味はありません。
どちらも同様に「害」という文字を含む言葉ですが、言葉の持つニュアンスが異なるので注意してください。
「弊害」を使いこなそう

今回は「弊害」という言葉を紹介しました。
特に、少しマイナスな物事についての発言は、スマートに伝えたいですよね。
混同しがちな「障害」「支障」との違いは、「妨げになるか」あるいは「害になるか」の違いです。
誤用しないように注意しましょう。