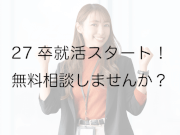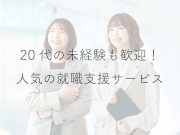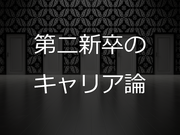Top > ライフ > お金/節約/貯金/税金
所得税とは?税率の変遷、計算方法、いくらから所得税がかかるのかなど解説。所得控除に関する情報も

納税は日本国民の義務なので、必ず納めなければなりません。
ただ、実際のところ「所得税って何?」と思われる方もいるでしょう。
筆者も会社員時代は、所得税の知識がまるでありませんでした。
本記事では、経理の専門家である筆者が、所得税の制度、税率、計算方法などを解説します。
終盤では、節税に役立つ「所得控除」についても紹介してあります。
これを利用すれば、あなたの税額が数千円、数万円単位で減る可能性もありますよ。
最後までお見逃しなく!
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】所得税とは?税率の変遷、計算方法、いくらから所得税がかかるのかなど解説。所得控除に関する情報も
平成49年12月31日までは、所得税とは別に「復興特別所得税」も発生しているので増税中
所得税・住民税を1円でも節税したい人は、「所得控除」を利用しよう!
所得税って一体なに?

はじめに、所得税の概要を簡単に説明します。
所得税が何に対してかかっている税金かも記載してあるので、よくわからないという方は飛ばさず読んでみてください。
課税対象額(所得)の金額によって生じる税金を指す
所得税は明治時代に創設された税制で、所得を基に計算される税金を指します。
収入に対して発生する税金ではないのでご注意ください。
収入は税引前の金額(会社員の場合は額面総額)を指し、所得は「給与所得控除(会社員対象)」、「経費、青色申告特別控除(個人事業主対象)」、「所得控除(全納税者対象)」などが差し引かれた金額を指します。
年収が高くても、控除額が増えれば所得税の額は減るので覚えておきましょう。
所得の種類とは?
所得は、主に下記の種類があります。
給与所得
給与所得は、「会社員・公務員」の所得を指します。
事業所得
事業所得は「個人事業主」の所得です。
例えば、コンサルタントをメインにしているのであれば、コンサル業務によって発生した所得を指します。
個人事業主のなかには、メイン事業とは別事業を行う方もいますが、場合によっては雑所得になるケースもあるので気を付けましょう。
不動産所得
不動産所得は家賃や駐車場収入など、不動産によって生まれた所得を指しますが、ややこしい所得です。
なぜなら、場合によっては「事業所得」としてカウントされるケースがあるからです(例.建物を宿泊施設として運営するなど)。
また、今話題になっている民泊も不動産所得ではなく、場合によっては雑所得(自宅に宿泊させる)として計上される場合もあります。
不動産を使いビジネスを行うときは、税理士などに確認することをおすすめします。
配当所得
配当所得は、「株価の値動き」や「株主配当金」によって出た儲けを指します。
ほとんどの所得は金額によって率が変わりますが、配当所得の税率は一律20.315%で統一されています(上場株式の場合)。
株式だけではなくFXの儲けも一緒の税率です。
言ってしまえば、国民が均等に支払う「消費税」と一緒の類なのです。
雑所得
雑所得は、どの所得にも当てはまらない所得を指します。
先述した民泊(自宅へ宿泊させる場合)もそうですし、ビットコインの利益もこれにあたります。
日本の所得税は「累進課税」が採用されている
累進課税とは、所得が多くなるにつれて税率が高くなる制度です。
現在の最大所得税率は「45%(年間の所得が4000万円以上の方対象)」となっています。
これは、収入による格差を縮小させる意味合いを込めて設定されています。
平成49年12月31日までは、所得税とは別に「復興特別所得税」も発生しているので増税中
所得税とは別に2013年(平成25年)1月〜2037年(平成49年)12月までは、「復興特別所得税」が発生します。
これは、所得税の金額に2.1%上乗せされる制度です。
仮に所得税が10万円の人であれば、平成49年までは「102100円」納税しなければならないということです。
パート・バイトの所得税はいくらから発生するの?

パートやバイトだと、所得税が発生するケースとしないケースがあります。
この章では、所得税が発生するボーダーラインを見てみましょう。
月収ベースで見ると8.8万円
毎月の収入が8.8万円未満だと、パート・バイトの所得税はかかりません。
8.8万円を超えると、最低でも数百円程度の所得税がかかるので注意しましょう。
年収ベースでみると103万円
年収ベースでみると103万円未満だと、所得税はかかりません。
103万円の場合、12で割ると「85833円」で、さきほど紹介した8.8万円とは異なる金額になります。
これは、月収ベースの計算と年収ベースの計算では、違う金額が算出されるからです(年収ベースの場合、控除制度が利用されるため)。
また、バイトの給料が年収ベースで103万円未満の場合でも、副業などの別所得を加えて103万円を超える場合は所得税がかかるので気を付けましょう。
所得税の税率がどのように変更されてきたか見てみよう

所得税の税率は、昔から今の税率だったわけではありません。
この章では、平成元年から税率がどのように推移してきたか見てみたいと思います。
平成元年
平成元年はバブル景気真っただ中で、業績が良かった企業も多かった年です。
所得税率は下記の通りです。
- 10%(〜300万円)
- 20%(〜600万円)
- 30%(〜1000万円)
- 40%(〜2000万円)
- 50%(2000万円〜)
平成7年
平成7年はWindows95が販売された年で、パソコンが身近になりました。
所得税率は下記の通りです。
- 10%(〜330万円)
- 20%(〜900万円)
- 30%(〜1800万円)
- 40%(〜3000万円)
- 50%(3000万円〜)
平成11年
平成11年は西暦で1999年だったため、翌年システムエラーを起こすのではないか(2000年問題)と大騒動になった年です。
所得税率は下記の通りです。
- 10%(〜330万円)
- 20%(〜900万円)
- 30%(〜1800万円)
- 37%(1800万円〜)
平成19年
平成19年は、はじめて「東京マラソン」が開催された年です。
当時は、東京の車道をランナーが走れるというので、大きな話題となりました。
所得税率は下記の通りです。
- 5% (〜195万円)
- 10%(〜330万円)
- 20%(〜695万円)
- 23%(〜900万円)
- 33%(〜1800万円)
- 40%(1800万円〜)
平成27年〜現在
平成27年は、世界体操大会で日本男子が37年ぶりの金メダルを獲得した年でした。
所得税率は下記の通りです。
- 5% (〜195万円)
- 10%(〜330万円)
- 20%(〜695万円)
- 23%(〜900万円)
- 33%(〜1800万円)
- 40%(〜4000万円)
- 45%(4000万円〜)
所得税の計算方法を実際に見てみよう

この章からは、実際に所得税の計算方法を見てみましょう。
「会社員・公務員」と「個人事業主」とでは、計算方法が違うので2パターン紹介します。
1.会社員・公務員などの計算の流れとは?
会社員・公務員の所得税を計算は、3つのステップを踏む必要があります。
なお、国税庁より発表された会社員の平均年収は「421万円」だったので、月給「35万800円」(421万円を12等分した金額が35万833円だったため)で計算します。
①月ごとに月給を基に所得税が計算される
会社員・公務員の場合は、毎月の給料支給日に所得税が発生する仕組みです。
月給の場合は社会保険料(厚生年金保険料、雇用保険料、健康保険料)を控除した金額を基に計算します。
計算式は、「350800円-32098円(350800円×18.3%÷2)-1052円(350800円×3÷1000)-17382円(350800円×9.91%÷2)」で、「300268円」が所得税の計算で使われる金額(課税対象額)です(厚生年金保険料・健康保険料の額が「÷2」がされている理由は、50%は事業者負担となるためです)。
課税対象額が分かったら、「給与所得の源泉徴収税額表」を利用して税額を算出します。
この表は、税額が分かる表です(給与所得の源泉徴収税額表がなければ、所得税額を計算できません)。
課税対象額は「300268円」なので、表の左列にある「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」の区分が「299000以上から302000未満」の行(横一列)を見ます。
扶養親族等の数によって、金額が違います。
扶養親族等の数が0人だと「8420円」、1人だと「6740円」となり、扶養親族等の数が増えるにつれて所得税額は減る仕組みとなっているのです。
②賞与発生時も所得税が計算される
賞与の際も所得税額は計算されますが、給料発生時と計算方法は違います。
「前月の税引前給与から社会保険料を引いた金額」を基に計算するのが原則です。
さらに、「賞与に対する源泉徴収額の算出率の表」を使用するため、「給与所得の源泉徴収税額表」を使ってはいけません。
例えば、前月の税引前給与から社会保険料を引いた金額が「300268円」、扶養親族等の数が0人の場合だと、扶養親族等の数0人の列(縦のライン)を見ます。
列から当てはまる対象金額の場所を探します。
今回は「300(千円)以上、334(千円)未満」にあたるので、税率は「8.168」%です。
仮に1回の賞与金額が50万円、社会保険料の金額が10万円だとすれば、数式は「(50万円-10万円)×8.168%」なので、「32672円」が所得税発生額です。
③年末調整時に、年収ベースで計算した源泉徴収額と、月ごとで計算した所得税額を比べ、月ごとの所得税額を多く支払っていた場合は還付される
毎年12月末になると1年間で天引きされた所得税額と、年収ベースで計算された源泉徴収税額が比較されます。
その後、月々の所得税額が源泉徴収額を超えていた場合、納税者へ還付されます。(年収ベースで計算する場合、給与所得控除が適用されるため、還付されるケースが多いです)。
2.個人事業主(自営業含む)
個人事業主の場合、会社員・公務員と計算方法は全く違うので要チェックです!
個人事業主の場合は、年間の所得額のみで計算される
会社員・公務員と違い1カ月単位に計算されることはなく、年間の所得額(課税対象額)に税率をかけて計算完了です。
仮に年収600万円、経費200万円、所得控除が50万円だった場合、「600万円-200万円」で1年間の所得額は「400万円」。
その後、所得控除が50万円引かれるので、課税対象額は「350万円」です。
最後に、所得税の速算表に当てはめると「350万円×20%-427500円」で、1年間の所得税額は「272500円」となります。
所得税・住民税を1円でも節税したい人は、「所得控除」を利用しよう!

所得税・住民税など節税したい読者も、いるのではないでしょうか?
私も、節税制度を活発に利用して、1円でも多く手元にお金を残したいので気持ちは分かります。
そこで最後の章では、節税として使える代表的な所得控除を紹介します。
1.扶養控除
扶養控除は、扶養親族がいる際に利用できる制度です。
条件は、下記4つです。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(出典: 国税庁 )
控除の対象となる親族は、納税年度の12月31日現在の年齢が16歳以上の人を指します。
また、扶養親族は「一般の控除対象扶養親族(控除額38万円)」、「特定扶養親族(控除額63万円)」、「老人扶養親族(同居老親等は控除額58万円、同居老親等以外は48万円)」の3つに分けられます。
年齢や身分によって、細かく設定されているので税務署へ確かめることを忘れないでください。
2.配偶者控除
納税者に配偶者がいる場合は配偶者控除の利用が可能です(内縁関係の場合は利用できません)。
条件は、扶養控除で紹介した(2)〜(4)の内容です。
一般の控除対象配偶者の場合は「38万円」、老人控除対象配偶者(その年の12月31日現在で70歳を超えている)の場合は「48万円」控除されます。
ただ、平成30年以降の控除額は、納税者の合計所得金額が900万円を超えた場合、控除金額も減るので注意してください。
3.生命保険料控除
生命保険料控除は、民間の保険会社において契約している方が使用できます。
「一般保険、介護保険、個人年金」の3つの枠が組まれており、各4万円まで控除対象額に組み入れられるので、3つ合わせて最大12万円控除されます。
確定申告前になると、保険会社より申告額が記載された「控除証明書」が送られてくるので、面倒な計算をする必要もほぼありません。(控除証明書を紛失しても、保険会社に再発行してもらえます)。
4.医療費控除
医療費控除は、1年間で10万円以上の医療費(医薬品代含む)が発生した方向けの制度で、10万円を超えた分の額を、医療費控除に組み入れられます。
仮に、1年間に支払った医療費が「12万円」であれば、10万円を引いた「2万円」分が控除対象額です。
しかし、医療費でも控除として認められないケースもあるので、確定申告前に税務署などで確認することを忘れずに。
5.ふるさと納税
ふるさと納税は、納税者が自治体へ寄付できる制度です。
自治体によっては納税した代わりに特産品を頂けるケースもあります。
なかには、黒毛和牛や高級フルーツの詰め合わせを送ってくる自治体もあるのです!
最近では、ふるさと納税を利用して食費を浮かせることも可能なのでおすすめです。
ふるさと納税〜確定申告までの流れ
ふるさと納税〜確定申告までの流れは、下記の通りです。
- 自治体を選び寄付をする
- 受領書が自治体より届く
- 確定申告時に、受領書を提出
- 「寄付した金額-2000円」の額が所得税・住民税の控除対象額となる
上記の流れを行うことで、ふるさと納税で支払った金額を控除対象にできます。
ただ、控除対象額の上限は、年収・扶養親族等の人数によって異なるので、確認したうえで制度を利用しましょう!
上限の目安額が載っているサイト(代表サイト: ふるさとチョイス )もあるので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
所得税は、収入ではなく所得を基に計算される
所得税は、所得(所得から所得控除を引いた課税対象額)によって計算されます。
また、所得金額が多くなるほど税率が上がるので、所得控除を使い節税しましょう(ただし、脱税はダメです)。
年度によって、所得税率は変わる
所得税率は、数年に一度変わります。
所得税の計算をする際は、最新の資料( 国税庁のホームページ に載っています)を手にしたうえで計算してください。
所得税を支払うのは国民の義務です。
納税を怠ると重加算税・延滞金などが加算されて税務署よりお灸を添えられます。
現在はマイナンバー制度ができたので、税金から逃れることはほぼ不可能です。
ぜひ、国民の義務をしっかりと果たし、健全な確定申告を行いましょう!
※本記事に掲載されている内容などは、2018年1月現在のものです。