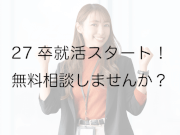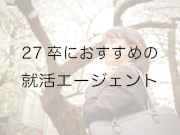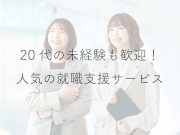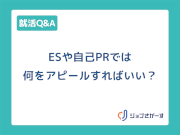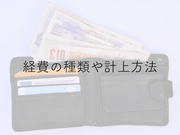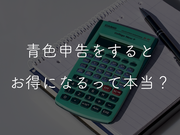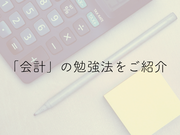テレワークってどんな働き方?メリットやデメリット、政府の方針は?

勤務先に通勤する代わりに、インターネットを利用しながら自宅やコワーキングスペースなどで仕事をするスタイルの働き方のことを指しています。
政府も推奨しているこちらの働き方ですが、実際にどのような仕事なのか、問題点はないのか、など疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで本記事では、テレワークの仕事内容やメリット・デメリットなどについてご紹介いたします!
テレワークを探すのに役立つサービスもご紹介いたしますので参考にしてください。
本ページに掲載のリンク及びバナーには広告(PR)が含まれています。
【目次】テレワークってどんな働き方?メリットやデメリット、政府の方針は?
テレワークって何?「自宅で勤務する」という働き方の魅力や実態をご紹介
テレワークって何?「自宅で勤務する」という働き方の魅力や実態をご紹介

これまで当たり前だった働き方をガラリと変える、「テレワーク」というワークスタイルを耳にしたことはありますでしょうか。
テレワークは、雇用先の企業のオフィスやミーティング室ではなく、自宅やカフェで仕事ができるという魅力があります。
そんなテレワークの仕事内容やメリット・デメリット、テレワークに対する政府の方針などについて、以下でご紹介していきます。
こちらの記事を通して、テレワークに興味を持って頂けると幸いです!
テレワークの仕事内容とは?

そもそも、テレワークとは一体どのような仕事のスタイルなのでしょうか。
総務省 によると、「テレワークとは、ICT (情報通信技術) を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方」であると定義されています。
ICTは「information and communication technology」の略で、10年ほど前からIT (information technology) に替わる言葉として、行政機関や公共事業で使用されています。
近年のインターネットやデバイスなどの発達のおかげで、場所や時間に縛られることなく自由な形態で出来る仕事が増えてきていますが、そういった従来とは異なる働き方がテレワークと呼ばれているのです。
ちなみに、テレワークという単語は「離れたところ」を意味する「tele」と「働く」を意味する「work」を合わせて作られた造語です。
テレワークの種類
そんなテレワークは、どの仕事もひとくくりにされていはいるものの、実は「雇用型」と「自営型」と呼ばれる主に2種類の働き方に分けられます。
・ 雇用型
総務省によると、「企業に勤務する被雇用者」が行うテレワークの形態は、雇用型と呼ばれています。
こちらのタイプのテレワークには、自宅を主な就業場所としている「在宅勤務」と、場所にとらわれず様々な環境で仕事を行うことができる「モバイルワーク」、そしてテレワークセンターやサテライトオフィス、スポットオフィスといった環境を主な就業場所としている「施設利用型勤務」の3つのタイプがあります。
なお、テレワークを実施する頻度によっても種類分けがされており、頻繁にテレワークを行う場合は「常時テレワーク」と呼ばれ、テレワークの勤務時間が週1〜2日であったり午前中のみの勤務に限られていたりする場合は「随時テレワーク」と呼ばれています。
・ 自営型
雇用型とは異なり、特定の企業に勤務するのではなく、自分で事業を展開している場合は「自営型」と呼ばれるテレワークの形態に入ります。
自営型のテレワークは、個人誌業者や小規模事業者が主な対象となっており、仕事の内容によって2つの種類に分けることができます。
1つ目は、独立自営の度合いが高く、専業性が高めの仕事を行っているテレワークが当てはまる「 SOHO」というタイプです。
SOHOとは「small office home office」の略で、個人事業者や小規模な事業者のことを意味するほか、事務所を離れてネットワークを利用しながら勤務をする形態のことを指すこともあります。
もう1つは「内職副業型勤務」と呼ばれるタイプで、SOHOとは反対に独立性および専業性があまり高くなく、仮に他の人が仕事を行っても容易に仕事を進めることができるものを指しています。
テレワークの仕事内容
テレワークの働き方は多様な種類の仕事で取り入れることができ、管理職、技術職、事務職などでもテレワークの形で仕事を行うことができます。
その中でも、特に事務職やIT関係など、職場でコンピューターに向かって働いている人たちは、そのワーキングスタイルをそのまま自宅に移動させるだけでテレワークを行うことは十分可能です。
他にも、データの入力、プレゼンに使用する資料や企画書の作成、電話やメールを通した連絡などといった仕事であれば、わざわざ通勤せずとも自宅でテレワークとして進められます。
さらに、テレワークには向いていないと思われがちな、外回りが多い営業職もテレワークを活用して行うことができます。
どういうことかというと、毎朝会社に通勤してから営業に行くよりも、自宅からそのまま真っ直ぐ営業先へ向かった方が時間も体力も節約できますよね。
そうすることで、1日でより多くの場所を訪問することができたり、仕事が早く終わったりということも可能です。
このように、営業職でもテレワークを採用してより効率的に働くことができるようにもなります。
反対に、テレワークに向いていない仕事があるのも事実です。
たとえば、パン工場や製麺所などの食べ物を製造する仕事や、家具の製造工場などのモノを作る仕事では、テレワークを実施することは難しいです。
また、介護施設、保育園、学校などの環境での仕事や、レストランやコンビニなどのサービス業も、面と向かったコミュニケーションが必要なのでテレワークは取り入れづらいでしょう。
前述した通り、ICTを利用して行うことができる仕事がテレワークに向いているということになります。
テレワークのメリット・デメリットとは?

テレワークの基本的な仕組みをご説明したところで、以下でテレワークのメリット・デメリットをいくつかご紹介していきたいと思います。
これまで日本社会で問題となっている長時間労働や満員電車などの解決策と期待されているテレワークについて、様々な観点からメリットとデメリットを考えてみましょう。
テレワークのメリット
・ 時間を有効に利用することができる
テレワークのメリットの中でもっとも大きいものが、時間をより有効的に活用することができるという点ではないでしょうか。
オフィスやミーティング会場に向かうまでの通勤時間に、毎日片道1時間以上をかけている人たちはたくさんいます。
たとえば、通勤時間が往復で毎日2時間30分かかる職場で週5日働くとすると、1ヶ月では少なくとも50時間を通勤に費やしていることになります。
テレワークを行うことで、これだけの時間を一気に節約することができるようになり、家族や友人とより多くの時間を過ごしたり、趣味に時間を費やしたりすることができるようになります。
さらに、満員電車の中で押しつぶされながら通勤したり、通勤ラッシュの渋滞に巻き込まれてイライラしたりといった、通勤に関するストレスや疲労をなくすことができるのも大きなメリットです。
現在、通勤やオフィス内での活動によって奪われてしまっている貴重な時間はもちろん、体力や精神力も、テレワークにスイッチすることで大幅に節約することができます。
・ 雇用先での人間関係でのストレスが少なくなる
通勤型の仕事よりもテレワークを好む人たちの多くが口を揃えて言うのが、テレワークで働いていると人間関係でストレスが溜まりにくいということです。
多くの職場では、同僚や上司の顔色を伺ったり、話を無理に合わせたりという、ストレスがたまりやすい環境で働いている人たちがいます。
パワハラやセクハラなどに悩まされているものの、やめてとほしいと言うことができずに日々辛い思いをしているという人たちも少なくありません。
そのような、ストレスが溜まりやすい環境で仕事をするよりも、テレワークを使用して自宅やお気に入りのカフェなどで周りの目を気にせずに働くことができるという点が、大きなメリットであると捉える人は多いようです。
・ 好きな場所に住むことができる
通勤をしなくて良くなるということは、どこに住んでいても働くことができるということです。
つまり、東京に本社がある企業で働きながら北海道の広い牧場のそばに住んだり、大阪の企業に勤めながら東京や神奈川などの首都圏に住んだりと、自分の好みや希望のライフスタイルに合わせて好きな場所に住むことができます。
そして、テレワークでは海外に住みながら働くことも可能です。
ハワイやフィリピンなどのトロピカルな島でリラックスした生活をおくりたいという場合や、結婚相手が海外転勤になってしまった場合なども、仕事への支障を最低限に抑えながら引っ越しをしやすくなっています。
・ 仕事とプライベートとのバランスが取りやすい
もう1つのテレワークのメリットが、自宅で働けることで仕事とプライベートを両立させやすくなるというものです。
たとえば、妊娠や出産のために一時休暇を取る女性の中には、「通勤は難しいけれど、仕事自体を行うのに支障はない。働ける日は働いてお金を稼いでおきたい。」と考える人たちがいます。
そういう場合は、長時間の通勤や職場でのつわりを心配しなくても良いテレワークが魅力的であると言えるでしょう。
また、子どもを出産した後も、自宅で子どもの面倒を見ながら勤務を続けることができるので、休暇を伸ばして収入が減ったり、育児のために仕事をやめたりということをしなくても良くなります。
子どもが体調を崩したときにも、1日中付き添いながら仕事をこなすことができるのは嬉しいですよね。
また、子どもの面倒だけでなく、親の面倒を見る働き盛りの人たちも大勢います。
特に親の介護が必要な場合は、自宅で勤務をしながら介護も同時に行えるライフスタイルを希望する人たちの声が大きくなりつつあります。
上記の「好きな場所に住むことができる」というメリットにも繋がってきますが、親が遠方に住んでいる場合は介護のために仕事をやめなくてはならないという状況にもなりかねません。
仕事を続けながら、かつ引っ越して親と一緒に住み始めるということができるのもテレワークのメリットです。
・ 怪我や病気で職場に行けないときでも働くことができる
いつ何が起こるかわからない人生では、ある日突然怪我をしたり病気にかかったりしてしまい、自宅療養を余儀無くされる場合もありますよね。
そんな状況でも、「資料まとめくらいならできる」、「しばらく外出はできないけどテレビ通話などでミーティングには参加できる」などといった理由で仕事を継続したいときが出てくることもあると思います。
そんなときにテレワークで勤務をしていれば、大事な仕事に穴を開けたり収入が減ったりすることなく、自宅で勤務を継続することができます。
テレワークのデメリット
・ 仕事とプライベートとの切り替えが難しい
毎日通勤をして、オフィスにある自分のデスクで仕事をし、帰宅時間になったら仕事を終えて帰宅する・・・
このような環境の中では、仕事場でやるべきことをやり、帰宅後は食事や買い物、映画鑑賞などを楽しむというように仕事とプライベートとのメリハリがしっかりと付いています。
しかし、テレワークでの勤務をする場合は、同僚や上司にもよりますが、早朝や夜遅く、さらには休日になっても電話やメールで仕事の連絡が来ることがあるかもしれません。
さらに、その日の分の労働時間が終了しても、仕事が残っていたら時間外労働を行わなければいけなくなる場合もあります。
この場合、家にいながらも家族と過ごす時間や自分のための時間が削られてしまうことになります。
そのため、しっかりと仕事の時間とプライベートの時間との区別がつけられるような働き方が求められます。
・ 集中するのが難しい
テレワークのもう1つのデメリットは、集中力が欠けやすいという点です。
仕事の内容や、仕事をしている人の性格、そのときの状況などにもよりますが、上司や同僚がいる職場で自分の仕事をこなすのと、自分や家族しかいない自宅で仕事を行うのでは、後者の方がプレッシャーが低く、それに合わせて集中力も下がってしまうということが起こり得ます。
ついつい休憩を取りがちになってしまったり、子どもの様子が気になり頻繁に様子を確認しすぎてしまったり、自分の周りの様々なものに気を取られすぎてしまって集中が長続きしないという状況になってしまうことも。
これを防ぐためには、上記の「仕事とプライベートとの切り替えが難しい」というデメリットと同様に、自らが強い意志を持ってしっかりとメリハリをつけて仕事を進めていく必要があります。
・ コミュニケーション不足が発生しがちである
テレワークの3つ目のデメリットは、面と向かっての上司や同僚とのやりとりが減ることによるコミュニケーション不足です。
部署内の同じチームのメンバーや上司、さらには取引相手などともインターネットや電話を介してのやりとりが基本となります。
すると、社内の大事な情報やニュースが伝わりづらくなったり、表情やジェスチャーが見えない分コミュニケーションの中で誤解が生まれてしまったりということが起きる可能性が上がります。
また、分からないことや困ったことがあるときにすぐにアドバイスや説明をしてくれる相手がいるとは限らないことも、テレワークの不安要素になるかもしれません。
相手の顔が見えづらいテレワークでは、メールや電話、テレビ電話などを活用して円滑なコミュニケーションを取ろうとすることが重要となってきます。
テレワークがこれから伸びる働き方ってほんと?

上記の通り、メリットもあればデメリットも見受けられるテレワークですが、日本政府としてはそんなテレワークをこれからさらに推進していきたいという狙いがあるようです。
そうというのも、実は2018年7月時点の現在からちょうど1年前の2017年の7月に、総務省が「テレワーク・デイ」の第1日目を実施したのです。
「テレワーク・デイなんて初めて聞いた」という方のために簡単にご説明すると、昨年の2017年から東京オリンピックが開催される2020年までの毎年、7月24日を「テレワーク・デイ」として、日本国内の参加企業および団体による一斉のテレワークを実施することが発表されています。
ちなみに、なぜ7月24日なのかというと、その日が2年後の東京オリンピックの開会式が予定されている日だからです。
昨年の第1回テレワーク・デイでは、およそ950の企業・団体が参加し、計およそ6万3千人もの人たちがテレワークを実施しました。
第2回目となる2018年は、「テレワーク・デイ」から「テレワーク・デイズ」と複数形の名称に変更され、7月23日から27日までの5日間のうち、24日を含む計2日間以上のテレワークの実施が呼びかけられています。
テレワークだけでなく、時差出勤やフレックスタイム制度などの多様な働き方が奨励されており、延べ10万人を超える参加者を目標に掲げる国民運動プロジェクトと位置付けられています。
みなさんのお勤め先では、テレワークやフレックスタイム制度は実施されましたでしょうか。

日本政府としては、地域経済の活性化や大規模災害対策、地球温暖化の抑止など、日本が抱えている様々な問題をテレワークを通して改善させていきたいという思いがあるようです。
また、近年パワハラや長時間労働、過労死など、多くの問題が浮かび上がっている日本の働き方を良い方向に変えていくためにも、テレワークの導入に力を入れています。
総務省からはテレワークを推進するパンフレットやテレワーク導入モデルを説明したガイドなども発表されており、テレワークを導入することによる企業側のメリットや導入のプロセスなどについて詳しく説明されています。
テレワーク導入モデルのガイドでは、「この業界はそもそもテレワークには向いていない」、「目の前に部下がいないと仕事をしているか不安」などといった「食わず嫌いな層」についても言及しているので、テレワークにいまいち好感を示していない上司の対処法も学ぶことができます(笑)
さらに、転職をサポートする求人ウェブサイト「 エン転職 」が2017年の6月上旬から7月上旬の1ヶ月間にわたって実施したウェブアンケートでは、「テレワークで働いてみたい」と回答した人たちの割合は、全体のおよそ50パーセントにものぼりました。
それに反して、テレワークを行ったことがある人たちの割合は全体の5パーセントほどとなっており、そのうちのおよそ40パーセントは「またテレワークで働きたい」と答えていました。
こちらのアンケートを通して、日本で働く多くの雇用者がテレワークを希望していることが分かりました。
政府の働きかけと雇用者の賛同によって、テレワークによる日本社会の「働き方改革」が始まりつつあるわけです。
テレワークの仕事に役立つサービスをご紹介

これまで、テレワークとはどのような仕事なのか、メリット・デメリットにはどのようなものがあるのかといったことについてご説明をしてきました。
最後に、テレワークを探したりテレワークについて学んだりするのに役立つオススメのサービスをご紹介していきます。
政府が主体となってこれからより推進されていくテレワークですが、企業によっては導入に何年もかかる場合もあると思います。
「テレワークの働き方を希望するが、上司や企業の賛成を得られない」という方は、これを機に思い切って転職を考えてみるのも1つの手かもしれません。
自分に合う仕事を、自分に合うスタイルの勤務方法で始める良いチャンスとなるかもしれませんので、ぜひ以下でご紹介するサービスを利用してテレワーク探しや知識の習得をしてみてはいかがでしょうか?
Indeed
世界でナンバーワンの「求人特化型検索エンジン」であるIndeedは、世界中の求人情報が掲載されている世界でも最大級の求人サービスです。
日本でのサービス利用者は毎月1,000万人を超えており、テレワークの求人情報も豊富に掲載されています。
こちらのサービスのオススメポイントは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで行うように、「キーワード」と「勤務地」を入力して検索ボタンを押すだけで検索結果の一覧を見ることができることです。
今回の場合であれば、キーワードの部分に「テレワーク」と入れればテレワークの求人情報を見ることができます。
シンプルなシステムと豊富で見やすい求人情報がある求人サービスをお探しの方にオススメです。
※「Indeed」のウェブサイトへのアクセスは こちら から。
PARAFT
「就業者が働く場所や時間を選択できる働き方を導入している、あるいは導入を検討している企業の求人情報をご紹介する転職・求人 WEBメディア」であるPARAFTには、求人情報はもちろん、ビジネスマナーについての記事や就職活動に役立つイベントなどが掲載されています。
「働くママ」や「働き方改革関連法」など、人気のキーワードに関した記事も多数載っています。
また、運営しているツイッターでは最新の求人情報をリアルタイムでチェックすることができますよ。
「未来の転職求人マガジン」であるPARAFTで、理想のテレワークが見つかるかもしれません。
※「PARAFT」のウェブサイトへのアクセスは こちら から。
以上、テレワークの働き方や仕事内容、メリット・デメリットなどについてご紹介いたしました。
この記事を読んで、テレワークに興味を持っていただければ幸いです。
テレワークをしてみたいという方は、ぜひ上記のオススメサービスを利用して検索してみてくださいね!